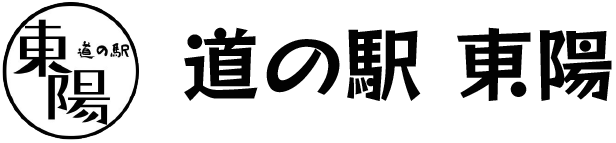石工の郷の由来
八代市東陽町は、急峻な山と平野が出会う地形を活かし、古くから棚田や段々畑が築かれてきました。
その畑を支える美しい石垣は、代々受け継がれてきた石積みの技術の結晶です。この石積み技術と、江戸時代に長崎から伝わったアーチ構造の技術が融合し、東陽地区には優れた石橋架橋集団が誕生しました。
こうして生まれた「石工の郷」は、今も多くの石橋や石垣が残り、地域の歴史と文化を今に伝えています。





種山石工について
種山石工(たねやまいしく)は、江戸中期から大正時代にかけて、八代市東陽町(旧種山村)を拠点に活躍した石工集団です。一説には長崎から移り住んだ林七が祖と言われています。
種山石工衆は記録には約50名残されており、全国的には「肥後の石工」として知られ、熊本県内だけでなく、九州各地や関東にも多くの石橋を架けました。著明な橋には、令和5年に土木建造物としては全国で初めて国宝に指定された「通潤橋」(山都町)や単一アーチとしては日本最大級の規模を誇る「霊台橋」(美里町)があります。
この種山石工の祖・林七の孫と言われる橋本勘五郎(はしもとかんごろう)は特に有名で、明治改元頃には政府に招かれ、神田筋違眼鏡橋、のちの万世橋を架橋しています。帰郷後は県内にに明八橋・明十橋・永山橋・高井川橋・下鶴橋を架け、福岡県八女市の洗玉橋架設を最後に、明治30年に75歳で没しました。
種山石工の歴史や技術は、八代市東陽石匠館(八代市東陽町北98-2 TEL:0965-65-2700)で詳しく知ることができます。